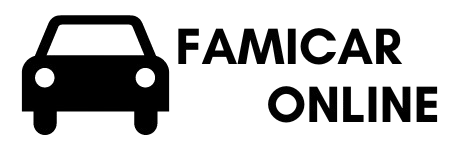ホンダのヴェゼルについてネットで情報を集めていると、「ヴェゼルに乗ってるのは貧乏人」なんていうドキッとするような情報を目にして、不安になったことはありませんか?
「もしかして、ヴェゼルを買うと周りからそんな風に見られちゃうの?」「無理して買ったと思われたくない」……そんな心配が頭をよぎる気持ち、私にも痛いほどよく分かります。せっかく高い買い物をするなら、誰だって後悔したくないし、周りからも「良い車選んだね!」って言われたいですよね。
でも、ちょっと待ってください。その「貧乏人」という言葉、本当に実態を表しているのでしょうか?実は、ヴェゼルの価格設定や実際のオーナー層のデータを深掘りしていくと、ネット上の噂とは全く異なる「意外な真実」が見えてくるんです。
ハリアーやカローラクロスと比較して悩んでいるあなたも、内装の質感や将来的な資産価値が気になっているあなたも、この記事を読めばきっとモヤモヤが晴れるはずです。
私が実際にディーラーで見積もりを取って感じたリアルな感覚や、市場の客観的なデータを交えながら、ヴェゼルという車の本当の価値を一緒に解き明かしていきましょう。
この記事を読むことで分かること
- 「貧乏人」というネットの噂が、実際の車両価格やオーナー層の経済力といかに乖離しているかという真実
- トヨタのハリアーやカローラクロスと比較した際に、ヴェゼルがあえて選ばれる明確な理由と立ち位置
- 内装の質感や具体的な維持費シミュレーションに基づいた、購入後のリアルな経済的負担と満足度
- 3年後のリセールバリュー(資産価値)が驚くほど高いというデータから見る、賢い投資としての側面
ヴェゼルが貧乏人の車という噂の真相

Googleの検索窓に「ヴェゼル」と打ち込むと、予測変換に「貧乏人」と出てくる……。
これは単なる悪口なのか、それとも何か根拠があるのか。火のない所に煙は立たぬと言いますが、この噂の裏側には、急速に高級化するコンパクトSUV市場に対する「認知の歪み」や、買えなかった人たちのコンプレックスが複雑に絡み合っているようです。
ここでは、具体的な金額やデータという「動かぬ証拠」を突きつけながら、なぜこのような噂が生まれたのか、その背景を徹底的に分析していきます。
新型ヴェゼル購入で後悔するポイント

まず最初に、ヴェゼルを購入して「失敗したかも……」と後悔しがちなポイントについて、包み隠さずお話しします。後悔の声として最も多いのが、「期待していた『高級車』のイメージと違った」という点です。
これ、実はヴェゼルのキャラクターをどう捉えているかで評価が180度変わってしまうんです。
例えば、あなたが「高級車=静かで、ふかふかのシートで、路面の凹凸を完全に消してくれる魔法の絨毯のような乗り心地」を想像してヴェゼルに乗ると、「あれ? 意外とゴツゴツするな」と感じるかもしれません。
特に18インチの大径タイヤを履いている「Z」グレードや「PLaY」グレードでは、路面の継ぎ目を越える時に「タンッ、タンッ」という硬めのショックが伝わってくることがあります。
これはホンダ車特有の「スポーティでダイレクトな走り」の味付けなのですが、トヨタ車のようなしっとりとした乗り味に慣れている人からすると、「安っぽい乗り心地」と誤解されてしまう原因になりがちです。
また、高速道路を走っている時のロードノイズに関しても、賛否が分かれるポイントです。
エンジン音はハイブリッドシステムのおかげで非常に静かなのですが、その分、タイヤが路面を転がる「ゴーッ」という音が目立って聞こえてしまうんですね。「300万以上払ったのに、もっと静かだと思った」という落胆の声は、こうした「期待値のミスマッチ」から生まれています。
さらに、クーペのような美しいスタイリングを優先した結果、後席の窓が少し小さくなっています。
これが外から見た時のかっこよさに繋がっているのですが、実際に後席に座った人、特にお子さんや閉所恐怖症気味の方からは「なんとなく圧迫感がある」「景色が見えにくい」という不満が出ることも。デザインの美しさと実用性は、時としてトレードオフの関係にあるということを、購入前に知っておく必要があります。
ここだけはチェック!購入前の注意点
- 足回りの硬さ:路面状況によっては突き上げを感じることがあります。必ず試乗コースにマンホールや段差がある道を選んで確認しましょう。
- ロードノイズ:静かなハイブリッドだからこそ、タイヤの音が気になる場合があります。オーディオを消して試乗するのがおすすめです。
- 後席の閉塞感:クーペルックの代償として窓が小さめです。家族全員でディーラーに行き、後ろの席に座ってみることを強く推奨します。
これらのポイントは、決して「車が悪い」わけではありません。むしろ、走りの楽しさやデザインの美しさを追求した結果なのですが、「高級セダンのような快適性」を求めて買うと、後で「貧乏くじを引いた」と感じてしまうリスクがあるのです。
乗り出し価格が高すぎて買えない現実

「ヴェゼルは貧乏人の車」なんて言っている人は、最近のヴェゼルの見積書を見たことがないのかもしれません。
はっきり言いますが、現行のヴェゼルは、もはやかつての「安くて手頃なコンパクトカー」ではありません。私自身、ディーラーで「e:HEV Z」の見積もりを出してもらった時、その総額を見て「えっ、嘘でしょ?」と二度見してしまいました。
具体的な数字を見てみましょう。一番人気のハイブリッドモデル「e:HEV Z」のメーカー希望小売価格は、およそ350万円前後です。これだけでも十分高価ですが、車は車両本体だけでは走れませんよね。
ここに、大画面の純正ナビゲーションシステム、ETC2.0車載器、ドライブレコーダー(前後)、フロアマット、そして長く乗るための点検パックやボディコーティング……と、ごく一般的なオプションを積み上げていくと、あっという間に50万円近く上乗せされます。
さらに税金や諸費用を加えると、乗り出し価格は400万円の大台を軽々と突破してしまうのです。
2024年のマイナーチェンジでは、原材料費の高騰や先進安全装備「Honda SENSING」の機能向上に伴い、さらに価格が上昇しました。400万円という金額は、日本の平均的なサラリーマンの年収(約460万円)に肉薄する数字です。手取り額で考えれば、年収の100%以上を車に突っ込む計算になります。
これを「貧乏人が買う車」と呼ぶのは、経済的な感覚として明らかに矛盾していますよね。むしろ、今のヴェゼルを購入できる層は、世間一般で見れば「勝ち組」に近い位置にいると言っても過言ではありません。
価格の上昇は、単なる値上げではなく、コネクティッド技術の搭載や安全性能の強化など、車としての「格」が上がったことの証明でもあります。
参考までに、正確な最新価格やグレードごとの装備差については、メーカーの公式サイトで確認することをおすすめします。カタログ上の数字だけでなく、実際にオプションを足していくとどうなるか、シミュレーションしてみると現実が見えてきます。
(出典:本田技研工業『VEZEL』)
オーナーの年収と客層のリアルな実態

では、400万円オーバーのヴェゼルを涼しい顔して契約しているのは、一体どんな人たちなのでしょうか? SNSやオーナーのコミュニティ、口コミサイトなどを分析していくと、そこには「貧困」とは程遠い、リアルなオーナー像が浮かび上がってきます。
最もボリュームゾーンとして目立つのが、「世帯年収800万円〜1000万円」クラスのアッパーミドル層です。
この層は、共働きで夫婦ともに正社員であったり、あるいは企業の管理職クラスであったりと、経済的にある程度の余裕を持っています。しかし、彼らがヴェゼルを選ぶ理由は「お金が余っているから」でも「高級車が買えないから」でもありません。キーワードは「ダウンサイジング」と「スマートライフ」です。
例えば、60代前後のシニア層。退職金を受け取り、住宅ローンも完済している彼らは、以前はオデッセイやクラウンといった大型車に乗っていたケースが多いです。
しかし、子供が独立して夫婦二人だけの生活になると、大きな車は持て余してしまいます。「質は落としたくないけれど、サイズは小さくして取り回しを良くしたい」。
そんなニーズに、ヴェゼルの「プレミアムなコンパクトSUV」という立ち位置がバチッとハマるのです。彼らにとってヴェゼルは、妥協して選ぶ車ではなく、「今の自分たちにジャストサイズな良品」なんですね。
一方で、20代〜30代の若年層オーナーも少なくありません。
彼らの多くは独身の実家暮らし、あるいはパワーカップル(高収入共働き夫婦)です。上の世代と違い、彼らにとって車は「移動手段」以上の意味を持ちます。スマホで音楽を聴くように車内Wi-Fiを使いこなし、休日はキャンプやグランピングに出かける。
そんな「映えるライフスタイル」を実現するための相棒として、デザイン性の高いヴェゼルを選んでいます。
| 年代 | 主な購入層の属性 | ヴェゼルを選ぶ心理・動機 |
|---|---|---|
| 20代〜30代 | 独身貴族・パワーカップル | 自己表現と体験への投資。「かっこいい車でキャンプに行きたい」「最新のデジタルガジェットとして乗りたい」というアクティブな動機。 |
| 40代〜50代 | 子育て世代(少数派) | 実用性と経済性のバランス。教育費がかかる時期だが、ミニバンを卒業したい層が、かっこよさと維持費のバランスで選択。 |
| 60代以上 | 資産保有層・リタイア組 | 賢いダウンサイジング。「大きな車はもう疲れるが、軽自動車では満足できない」という層が、安全装備と質感を求めて指名買い。 |
こうして見ると、どの世代においてもヴェゼルオーナーは「自分のライフスタイルを明確に持っている人たち」であることが分かります。「お金がないから仕方なく」ではなく、「自分の生活を豊かにするために、あえてこの車を選んでいる」。そんな賢い消費者たちが、ヴェゼルのメインユーザーなのです。
ハリアーとの比較で感じる劣等感の正体

ここが、多くの人が「ヴェゼル 貧乏人」というキーワードに囚われてしまう最大の沼かもしれません。そう、トヨタの超人気SUV「ハリアー」との比較です。
日本では長年、「ハリアー=成功者の証」「いつかはハリアー」みたいなブランドイメージが定着していますから、どうしても意識してしまいますよね。
悩ましいのは、ヴェゼルの新車価格(乗り出し400万円弱)が、中古のハリアー(80系前期モデルなど)の価格帯とガッツリ被ってしまうことです。
「同じ400万円出すなら、車格が上のハリアーを買った方が、周りから『いい車乗ってるね』って言われるんじゃないか?」「ヴェゼルを買ったら、『ハリアーを買うお金がなかった人』って思われるんじゃないか?」……そんな風に、他人からの評価を気にしてしまう気持ち、すごく分かります。
しかし、ここで冷静になって考えてみてください。中古のハリアーを選ぶということは、メーカー保証が短くなっていたり、タイヤやバッテリーなどの消耗品交換時期が迫っていたり、あるいは前のオーナーがどんな乗り方をしていたか分からないという「見えないリスク」を背負うことになります。
また、燃費性能や安全装備(自動ブレーキの検知範囲など)も、最新のヴェゼルと比べれば一世代前のものになる可能性があります。
対して、新車のヴェゼルを選ぶということは、最新鋭の安全運転支援システム「Honda SENSING」による守りを手に入れ、3年〜5年の手厚いメーカー保証を受けられ、誰の手垢もついていない真っさらなシートに座れるということです。これは「見栄」よりも「実利と安心」を優先する、極めて合理的な大人の判断だと言えませんか?
また、サイズ感の問題も無視できません。ハリアーは全幅が1855mmもあり、日本の狭いコインパーキングや住宅街の路地では気を使う場面が多々あります。一方、ヴェゼルは全幅1790mmと、取り回しの良さが抜群です。都内のマンションの機械式駐車場などでも、ヴェゼルなら入るけどハリアーはNG、というケースは意外と多いのです。
「どこへでもストレスなく行ける」という自由を手に入れるために、あえてコンパクトなヴェゼルを選ぶ。それは決して「貧乏」による妥協ではなく、「自分の生活環境に合わせた賢い選択」なのです。
他人の目線で車を選ぶと、いつまで経っても満たされません。「ハリアーの方が偉い」という古い価値観から脱却し、「自分にとって使いやすいのはどっちか?」という視点で選べば、劣等感なんて感じる必要は全くないんですよ。
カローラクロスより割高でも選ぶ理由

ハリアーとの比較以上に、頭を悩ませるのが「カローラクロス」との直接対決でしょう。同じ価格帯、同じハイブリッドSUV、そして世界のトヨタ。しかも、カローラクロスの方がボディサイズが一回り大きく、荷室も広いです。スペック表だけを見比べていると、「あれ? カローラクロスの方が安くて大きくて、パノラマルーフも付けられて……お買い得じゃない?」と思えてくるのも無理はありません。
実際、コストパフォーマンス(費用対効果)という意味での「物理的な量」を求めるなら、カローラクロスに軍配が上がります。同じ350万円で、よりたくさんの鉄と、より広い空間が手に入るわけですから。ここで「同じ値段なら大きい方が偉い」「装備が豪華な方が得」という価値観を持つ人が、ヴェゼルを見ると「小さくて割高=損している=貧乏くじ」と映るのかもしれません。
でも、それでも多くの人があえてヴェゼルを選んでいます。なぜでしょうか? それは、ヴェゼルにはカローラクロスにはない「感性に訴える価値」があるからです。その代表格がデザインです。カローラクロスがSUVらしい無骨さや実用性を重視しているのに対し、ヴェゼルは「クーペのような美しさ」や「塊感」を徹底的に磨き上げています。ボディ同色のグリルや、水平基調の美しいサイドラインは、見るたびに所有欲を満たしてくれる芸術性を持っています。
そして、ホンダ独自の特許技術である「センタータンクレイアウト」が生み出す魔法のような使い勝手。後席の座面を跳ね上げて、背の高い観葉植物やベビーカーをそのまま積み込める「チップアップシート」は、カローラクロスには絶対に真似できない芸当です。「普段はコンパクトで運転しやすいのに、いざという時は想像以上に荷物が積める」。このギャップこそがヴェゼルの真骨頂です。
さらに、走りの質も見逃せません。ホンダの2モーターハイブリッド「e:HEV」は、ほとんどの領域をモーターで走行するため、電気自動車のような滑らかさとレスポンスの良さがあります。カローラクロスのハイブリッドも優秀ですが、走りの爽快感やハンドリングの楽しさという点では、ヴェゼルが一歩リードしていると評価する評論家も多いです。
つまり、カローラクロスを選ぶのが「実用重視の買い物」だとするなら、ヴェゼルを選ぶのは「感性と体験への投資」と言えます。物理的な大きさや分かりやすい装備表の〇×では測れない、「乗っていて気持ちいい」「見ていて美しい」という感覚にお金を払う。それはある意味、とても贅沢で豊かな消費行動なのではないでしょうか。
ヴェゼルを貧乏人と断定する誤解を解く

前半では価格やライバル比較から誤解を解いてきましたが、後半ではさらに踏み込んで、「内装の質感」「維持費」「資産価値」という、より現実的でシビアな側面から検証していきます。「ヴェゼルは中身が安っぽいんじゃないか?」「維持費で生活が苦しくなるんじゃないか?」そんな不安を、具体的なデータと事実で吹き飛ばしていきましょう。
内装が安っぽいひどいという酷評の嘘
ヴェゼルの購入を躊躇させる大きな要因の一つに、ネット上の「内装が安っぽい」「プラスチックだらけでひどい」という辛辣な口コミがあります。300万円、400万円という大金を支払うわけですから、ドアを開けた瞬間に「うわっ、安っぽいな」なんてガッカリしたくはありませんよね。私も展示車を見るまでは、この評判をすごく気にしていました。
実際に実車を見て、触れてみて分かったのは、この「安っぽい」という評価は、評価する人の「高級感の基準」がどこにあるかによって大きく変わるということです。もしあなたが、一昔前の高級車のような、ピカピカのメッキパーツが輝き、木目調パネルがふんだんに使われ、ピアノブラックでテカテカしている……そんな「分かりやすい豪華さ」を求めているなら、確かにヴェゼルの内装は質素に見えるかもしれません。ヴェゼルには、そういった過度な装飾がほとんどないからです。
しかし、今のホンダが目指しているのは、そういった「足し算の豪華さ」ではありません。現行ヴェゼルの内装テーマは、徹底した「ノイズレス」と「ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)」の追求です。運転席に座ってみると分かりますが、視界の端に余計な凹凸や反射が入らないように、ダッシュボードは極めてフラットに設計されています。これは、運転への集中力を高め、疲れを軽減するための機能的なデザインなんです。
「プラスチックだらけ」という批判についても、よく見ると単なるコストカットのプラスチックではないことに気づきます。手が触れる部分にはソフトパッドが使われていますし、エアコンのダイヤルやスイッチ類は、回した時に「コリコリッ」という心地よいクリック感があるように、緻密なチューニングが施されています。見た目の派手さよりも、「触った時の感触」や「使い心地」にお金をかけているわけです。
さらに、ヴェゼルならではの「おもてなし機能」として外せないのが、「そよ風アウトレット」です。エアコンの風が直接顔や体に当たると不快ですよね。この機能は、ダッシュボードの両端にあるL字型の吹き出し口から、風を窓に沿って流すことで、車内全体を包み込むような穏やかな空調を実現しています。これなんて、見た目の豪華さには全く寄与しませんが、乗る人の快適性を第一に考えた、非常に贅沢な機能だと思いませんか?
「PLaY」グレードの内装は別世界?
特に個性的と言われる「PLaY」グレードでは、グレージュとブラックのコンビネーションカラーや、オレンジのステッチが採用されており、非常にモダンで明るい雰囲気です。「安っぽい」というよりは、「北欧家具のような洗練されたセンス」を感じさせます。古い価値観の高級感ではなく、新しい時代の豊かさを表現していると言えるでしょう。
つまり、ヴェゼルの内装を「安っぽい」と断じるのは、「装飾の多さ=高級」という古い物差しで測っているからに他なりません。「機能美」や「居心地の良さ」という現代的な視点で見れば、ヴェゼルの内装は価格以上の価値を持った、非常に考え抜かれた空間なのです。
維持費がきついと貧困に陥るリスク

「車両価格は頑張ってローンで払えても、維持費で生活が破綻するんじゃないか……」。そんな不安を抱えている方もいるでしょう。「コンパクトSUVだし、維持費なんてフィットやヤリスと同じくらいでしょ?」と甘く見ていると、後で痛い目を見る可能性があります。ここでは、忖度なしのガチな維持費シミュレーションを公開します。
まず、自動車税などの法定費用は排気量1.5L区分なので標準的ですが、問題はそれ以外のランニングコストです。例えば、ガソリン代。ハイブリッドのe:HEVは燃費が良い(実燃費で20km/L前後)とはいえ、昨今のガソリン価格高騰を考えると、年間1万キロ走れば約8万〜9万円はかかります。ガソリン車を選べば、さらにコストは嵩みます。
そして意外と見落としがちなのが、タイヤ交換費用です。
ヴェゼルの上位グレード(ZやPLaY)は、18インチというかなり大きなタイヤを履いています。これ、見た目は最高にかっこいいんですが、いざ交換するとなると、タイヤ4本で10万円〜15万円コースです。「軽自動車なら4本で3万円くらいだったのに!」という感覚でいると、車検のタイミングで顔面蒼白になること間違いなしです。
さらに、駐車場代(全国平均で月1万円と仮定)、任意保険料(車両保険込みなら月7〜8千円はザラ)、半年ごとのオイル交換やメンテナンス費用……これらを全て合算すると、年間の維持費はどうなるでしょうか。
| 費目 | 年間コスト目安(e:HEV Z) | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 30,500円 | 毎年5月の出費 |
| 車検・点検費用 | 約50,000円(年換算) | 法定費用+整備費の積立 |
| 任意保険料 | 約80,000円 | 車両保険あり・20等級想定 |
| ガソリン代 | 約85,000円 | 1万km走行・レギュラー170円/L |
| 駐車場代 | 120,000円 | 月1万円の場合(地域差あり) |
| 消耗品(タイヤ等) | 約30,000円(年換算) | 数年に一度の大きな出費を月割 |
| 合計(年間) | 約395,500円 | 月額換算:約33,000円 |
いかがでしょうか。車をただ置いておくだけでも、ならしてみれば毎月約3万3千円のお金が飛んでいく計算になります。もし、車両本体をフルローン(月々5万〜6万円)で購入していた場合、毎月の車関連の出費は合計で約9万円に達します。
手取り25万円の若手社員だとしたら、給料の3分の1以上が車に消える計算です。これを涼しい顔で払い続け、かつ貯金もできる……そんな家計管理ができている人を、誰が「貧乏」と呼べるでしょうか? ヴェゼルを維持し続けるということは、それだけで一定以上の「経済的な基礎体力」があることの証明になるのです。
「維持費がきつくて手放した」という話も聞きますが、それはヴェゼルが悪いのではなく、身の丈に合わない買い方をしてしまったケースがほとんどでしょう。
無理なローンを組んで買う若者の事情

「最近の若い子は、残クレ(残価設定ローン)で無理して高い車を買ってるから、見かけ倒しの貧乏だ」なんていう意地悪な意見を、ネットの掲示板などで見かけることがあります。
確かに、20代で400万円の車を買うのは、一昔前ならかなりハードルの高いことでした。しかし、私はこういった若者たちを「貧乏」だとは全く思いません。むしろ、彼らは独自の価値観を持った「チャレンジャー」であり、ある種のエリート予備軍だとさえ感じます。
今の20代は、生まれた時から不景気だった「悟り世代」や「Z世代」です。彼らは無駄な飲み会には行かないし、ブランド服にもそれほど執着しません。そんな彼らが、あえて数百万円の借金を背負ってまでヴェゼルを選ぶ。これは、単なる見栄ではなく、「自分の人生を豊かにする体験」への強烈な投資なんです。
彼らにとってのヴェゼルは、ただの移動手段ではありません。休日に友人とキャンプに行ったり、恋人とドライブデートをしたり、あるいは一人で好きな音楽を聴きながら夜の高速を流したり……そういった「エモーショナルな時間」を生み出すための装置です。スマホやPCと同じくらい重要な、自己表現のツールなんですね。
また、経済的な観点から見ても、彼らの選択はあながち間違っていません。今の車は安全性能が飛躍的に向上しており、事故のリスクが低減されています。古い安い中古車を買って事故や故障に怯えるよりも、最新の安全装備にお金を払うことで、将来のリスクを回避しているとも言えます。
「若いくせに生意気だ」という嫉妬交じりの批判は無視していいんです。自分の給料からしっかりとローンを返済し、大好きな車と過ごす時間を楽しんでいるなら、それは立派な「自立したカーライフ」です。無理なローンかどうかを決めるのは、外野の人間ではなく、オーナー自身の満足度なのですから。
中古市場での価値とリセールバリュー

最後に、ヴェゼルが「貧乏人の車」であるという説を、数字の力で完全に論破しましょう。それが「リセールバリュー(再販価値)」です。「貧乏人=お金の使い方が下手」という定義だとするなら、ヴェゼルを買う人はその真逆、つまり「買い物上手な投資家」であると言えます。
なぜなら、ヴェゼルは日本で販売されている数ある車の中でも、トップクラスに「値段が落ちにくい車」だからです。中古車市場の相場を見ていると、その強さに驚かされます。特に現行モデルのヴェゼルは、世界的なSUVブームや半導体不足による新車納期の遅れも手伝って、中古車相場が高値安定を続けています。
具体的なデータでお話しすると、一般的な国産車は3年乗ると新車価格の50%〜60%程度まで価値が落ちるのが普通です。しかし、ヴェゼルの場合、グレードや状態にもよりますが、3年後でも70%〜80%以上の残価率を維持しているケースがザラにあります。一時期は、ガソリンモデルの中古車が新車価格以上の値段で取引されるという異常事態すら起きていました。
(出典:本田技研工業『旧型車・年式ごとの情報』)
※公式アーカイブ等でモデル変遷を確認できますが、実勢価格は中古車サイト等の市場データに基づくものです。
リセールバリューが高いと何が得なのか?
- 次の車への乗り換えが楽:売却額が高ければ、それを次の車の頭金にすることで、持ち出し費用を大幅に抑えられます。
- 実質負担額の圧縮:「400万円で買って300万円で売れた」なら、3年間乗って実質100万円(月額約2.7万円)でヴェゼルに乗れたことになります。これは非常にコスパが良い状態です。
- 資産としての安全性:万が一、急にお金が必要になったり、ライフスタイルが変わって車を手放すことになっても、高く売れるのでローン残債で苦しむリスクが低いです。
つまり、リセールバリューを計算に入れてヴェゼルを買っている人は、表面上の価格(400万円)だけを見ているのではなく、「出口戦略」まで見据えて賢く資産運用しているのです。これって、むしろ富裕層の思考回路に近いと思いませんか? 「
高い車を買って損をする」のが貧乏への入り口だとしたら、「高く売れる車を選んで損を最小限にする」ヴェゼルオーナーは、間違いなく「賢者」なのです。
ヴェゼルは貧乏人の車ではない証明

ここまで、価格、維持費、内装、そしてリセールバリューと、あらゆる角度から「ヴェゼル 貧乏人」説を検証してきました。結論として言えるのは、この噂は完全に事実に反する、根拠のない偏見だということです。
改めて、今回明らかになった事実を整理してみましょう。
- 購入のハードルが高い:乗り出し400万円超の価格は、平均以上の所得がなければおいそれとは手が出せません。
- 維持する力が必要:月々約3万円以上のランニングコストを許容できる、安定した家計基盤が求められます。
- 賢い経済感覚:高いリセールバリューを理解し、資産価値の落ちにくい車を選ぶという、投資的な視点を持ったオーナーが多いです。
- 自分の価値観で選ぶ強さ:「ハリアーの方が偉い」「大きい方が偉い」という古いヒエラルキーに流されず、自分に必要なサイズと質を選択できる自立した精神を持っています。
もし、あなたがこれからヴェゼルを買おうとしていて、ネットの心ない言葉に不安を感じているなら、どうか自信を持ってください。あなたは決して「妥協」してヴェゼルを選ぶのではありません。現代の日本の道路事情、経済環境、そしてライフスタイルに最も適した「最適解」を選ぼうとしているのです。
ヴェゼルの運転席に座り、滑らかに走り出した瞬間、周りの雑音なんてどうでもよくなるはずです。「ああ、この車を選んでよかった」。そう思える日が来ることを、私も一人の車好きとして確信しています。あなたの賢い選択が、素晴らしいカーライフの始まりになりますように!